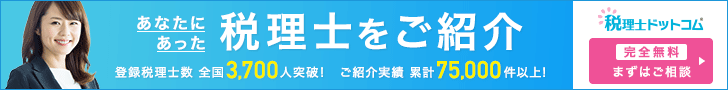アソシエイト弁護士の確定申告|申告期限ギリギリで焦らないために日頃からやっておくべき3つのこと
目次
弁護士業務は、並行してこなすべき業務が多く多忙です。
会計業務まで手が回らない!と思いつつも、これを外部の税理士に投げるということもできるほどの余裕まではない方も多いのではないでしょうか。
しかし、確定申告期限を過ぎてしまっては、青色申告控除の特典が受けられないばかりか、無申告による税金が加算されてしまい想定よりもかなり多くの税金を支払うこととなってしまいます。
そこで、今回は、自分で会計管理を行いたい新人弁護士の先生方に向けて、日頃から最低限やっておくべきことと直前では間に合わないことを確認していき、できるだけ確定申告の提出期限ギリギリで焦らないで済むようにしましょう。
なお、下記の税務に関わる事項については、弁護士として仕事をしている私が普段自身の会計管理を行う上で気にしている事項をまとめたものですので、税理士としての知識・経験に基づくものではありません。
確定申告とは
そもそも確定申告ってなに?
確定申告とは、簡単に言うと、税務署に対し、確定した所得の申告を行い、当該所得に対する税金(所得税)を清算する手続きのことです。
確定申告を行う義務がある人は?
個人事業主や労働者のうち、事務所(メインの収入)のほかに年20万円以上の収入(副業。会務活動の日当など)がある人が対象となります。
町弁のアソシエイト弁護士は、個人事業主として活動していることが多いと考えられますので、下記は、個人事業主を前提として記載します。
確定申告の提出期限はいつまで?
対象となる会計年度(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までです。
どんな税金を払うことになるの?
確定申告の提出に伴い、所得税を納付することになります。
また、確定申告の際に申告した所得をもとに、各地方自治体に対して、住民税を納付するほか、国民健康保険に加入している場合には、その算定され、納付することになります。
課税される範囲
極めて単純化すると、
売上ー経費ー控除=課税される利益
となります。
日頃から最低限やっておくべきこと
アウトライン
上記のように確定申告の際に必要な要素は、
- 「売上」
- 「経費」
- 「控除」
です。そのため、これらに関連する事情を日頃から集めて管理しておく必要があるということになります。
売上の観点
弁護士の成りたての頃に想定できる売上は、
- 所属事務所からの給与(名目は色々)
- 個人事件での弁護士費用
- 無料相談の日当
- 会務活動の日当
- ロースクールの補助業務
- 予備校関係の補助業務
などが考えられます。
売上の種類は、大きく2つに分かれます。
- 報酬
- 給与
です。
日頃からやっておくべきこと
源泉徴収の有無が異なりますので、別でまとめておくとよいでしょう。
また、特に会務活動の日当などは、弁護士会から振り込まれる際に、何の入金なのか分からないため、あとから特定ができなくなることがしばしばあります。
そのため、日頃から入金されたら、項目をメモするということをしておくと良いでしょう。
経費の観点
そもそも経費には、何を入れられるの?
何でも経費にできるというわけではありません。
売上を上げるうえで、絶対に必要な費用か否かで判断するのがいいでしょう。
そのため、事業に関連するというだけでは足りません。
例えば、スーツや革靴は、大きな金額であるため、経費に入れたくなりますが、必ずしもスーツ等はなくとも事業を遂行することは可能です。
そのため、スーツ等は、一般に経費としては認められないという見解が強いです。
日頃からやっておくべきこと
領収書の収集、管理、メモ
上記の観点で、経費として計上できる費用を支出した際には、領収書を保存しましょう。
この際、当該領収書に、何のための支出なのかということをメモしておきましょう。
その場でやらないと以外と日々の業務で忙殺されて、あとから何の領収書なのか思い出せないということも多々あります。
後述の会計管理ツールを使用するという場合には、スマホで撮影し、メモすることもできます。
定期的な支出の管理
毎月かかる費用というのもあるでしょう。
例えば、弁護士会費やサブスク関連の支出が考えられます。
エクセル等で管理する場合には、コピぺすることが考えられますし、後述の会計管理ツールを使用する場合には、よく使う項目としてセットすることができます。
控除の観点
各種控除は、確定申告の提出期限ギリギリの時点では、間に合いません。
会計の期間が、1月1日から12月31日であるのに対し、確定申告の提出期限は、翌年の3月中旬だからです。
そのため、各種控除の恩恵を受けたい場合には、当該会計年度の期間中に控除となり得る行動をしておく必要があります。
控除として考えられる項目
- 青色申告控除
- ふるさと納税
- 年金
- 生命保険等
- 寄付
が考えられます。
事前にやっておくべきこと
青色申告控除の特典を受けるためには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
また、ふるさと納税以下の各種控除は、当該会計年度内に支払ったもののみが対象になります。
特にふるさと納税は、所得に応じて控除可能なふるさと納税の金額が変動します。
会計年度の最後の年末時点で、会計関係がまとまっていないと、これが算出できません。
そのため、日頃から、会計の管理はしておく必要があります。
経費などの考え方を学ぶための教材|弁護士・事務職員のための法律事務所の確定申告入門
日々の業務の中でこなしていかなければならない作業ですので、ゼロから全て学習することは難しいです。
そのため、例えば、「これは経費として計上していいのだろうか」などと疑問を持った際には、そのつどGoogleで検索する方が早いです。
もっとも、Googleも万能ではありませんので、どうしても細かい部分についてわからなかったり、概念の説明から調べたいということもあるでしょう。
ただ、確定申告という広く一般向けの書籍を読んでも、弁護士プロパーの部分が分からないということもあります。
そこで、弁護士用に作られた書籍を1冊手元に置いておくのがよいでしょう。
会計管理のためにおすすめのツール|MoneyForward(マネーフォワード)クラウド
例えば、会計管理のツールを使うことで、以下のことができるようになります。
- 領収書から数字の自動検出
- 勘定科目の候補の提示
- 同一の項目についてセットの作成、自動で毎月引落しの反映
- 確定申告の提出の際の書面の半自動作成(質問に回答し、必要情報を入力するだけ)
会計管理は、エクセルなどで作成し続けても大丈夫です。
もっとも、毎回毎回仕分けを調べたり、確定申告用の書面を自分で作成するのは、意外と大変な作業です。
同様の作業はできるだけ省き、効率化して進めることで、本来の弁護士業務に支障ないように進めていきましょう。
そこで、会計管理のツールを利用することをお勧めします。
私も成りたてのあまり会計に動きのない頃は、自作のエクセルでも特に不便なく行えていましたが、段々と手持ちの案件が増え、個人事件の増加や経費に入れるべき支出が増えるほど対応が難しくなっていきました。
そのような中で、会計管理のツールを使用し始めたところ、各段に会計関係に割くべき時間が減りました。
MoneyForward(マネーフォワード)クラウド
私が一通り試してみた結果の感想としては、会計管理ツールは、そこまで差異はありませんでした。
上述したような、領収書の数字の自動検出などの機能は、いずれもありますし、あとは見た目などの好みなどかと思います。
そのような中で1つおすすめするとすれば、マネーフォワードは、スマホアプリでもありますが、普段使いとして、口座の紐づけなどがとても簡単に感じました。
他の会計管理アプリ|freee、弥生
他の会計管理アプリもまとめておきます。
いずれも登録は、無料でできますので、一通り使用感を比較してみて、一番しっくりくるものを使用するというので良いと思います。
freee
弥生のクラウド確定申告ソフト
色々見て来たけどどうしても税理士に頼みたい人向け
実際、極限レベルまで案件を抱えていると上記最低限やるべきことすらできないということもあり得ます。
そうすると、税理士を探すという場面においても、時間が掛けられないということになるでしょう。
そこで、税理士を紹介してくれるサイトを利用すると探す手間を大きく削ることができます。
日常的には、領収書を定期的に送り、管理してもらうほか、確定申告時期に駆け込むといった場合にも駆け込むことができます。